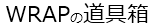母に最初の深い抑うつの症状がおきたとき、彼女には何のサポートもありませんでした。彼女が必要としていたサポートをどのように提供したらいいのか誰も知らなかったのだろうと思います。近しい家族は遠くに住んでいました。鉄道の仕事をしていた父は数週間続けて家を空けることがしょっちゅうでした。私たちは田舎に住んでいて、5人の子どもを一人で育てることは彼女にとって、とても荷の重いことだったのかもしれません。他の女性と話す機会もありませんでした。
もし最初に症状のエピソードが始まった時に、彼女を愛していた人たちや彼女の知っている世界から切り離され、病院にいくのではなく、愛情をもって気にかけてくれる友達や家族に囲まれていたとしたら、彼女の気持ちはどう変わっていただろうかと思うことがよくあります。彼女の毎日の日課をしばらくの間、肩代わりしてくれたかもしれないし、誰かが彼女を休暇旅行に連れ出してくれたかもしれません。多分、彼女が泣いている間、ただそばに座って耳を傾け、抱きしめていてくれただろうと思います。病院では、お互いに支えあうことを奨励するようなことは何も行われていませんでした。ごく限られた人数のスタッフが一人ひとりにサポートを提供することはできなかったようです。
幼心にわたしは母が病気になったのは私のせいだと思っていました。何が病気を引き起こしたのかはわからなかったのですが、私が正しいことを言えば、彼女は良くなって元気のままでいられると思っていました。ただ困ったことに、彼女と二人っきりになるといつも、私は何と言ったらいいのかわからなくなりました。
病院の雰囲気はその当時の州立精神病院の例にもれず、とてもひどいものでした。混雑していて、暗くて、においが立ち込めていました。彼女は女性40人の大部屋に入院していました。ベッドの間に小さな机があって、それだけが自分の持ち物をしまっておけるところでした。プライバシーなし。休まる時間なし。心の平静が得られるときがありません。彼女と同じくらい重いと診断された人が40人入院していまいました。彼女は食事がひどかったことを思い出すといっていました。母は料理をすることに長けていたので、食事のことはよくわかっていたのだと思います。医者と話す時間はほとんどなく、スタッフも数が少ないために話も満足にできず、回復のための薬も手に入らないという状況でした。良くなるとは誰にも期待されていませんでした。そこは人々を管理するタンクのようなもので、治癒やリカバリーの助けをする場所ではありませんでした。
当時(1940年代の後半から50年代の前半)は、精神薬が開発され精神療法やリカバリーに関心がよせられる以前のことです。躁うつ病と診断された彼女が経験していたのと同じくらい重い症状を持つ人たちは、家族や友達から忘れ去られて、病院の奥の病棟で一生を過ごし、一人寂しく死んでいくのだと思われていました。しかしケイトは違いました。8年にも及ぶ重症で幻覚をともなう躁とうつを繰り返していた後に良くなったのです。そして、その後82歳で亡くなるまでの37年間ずっと元気だったのです。